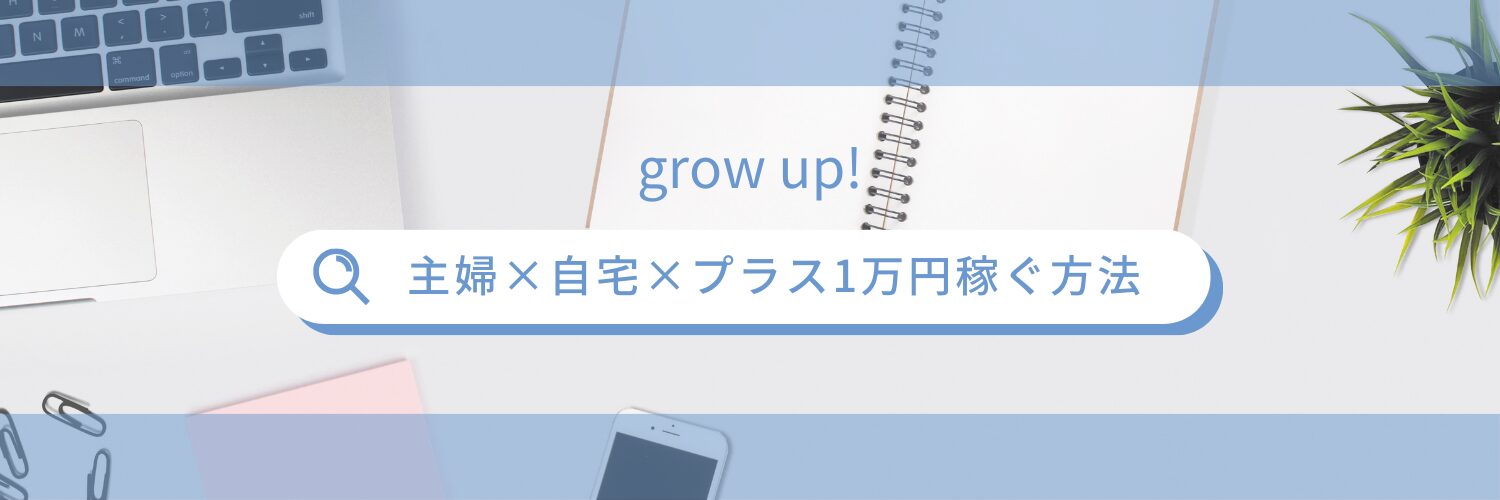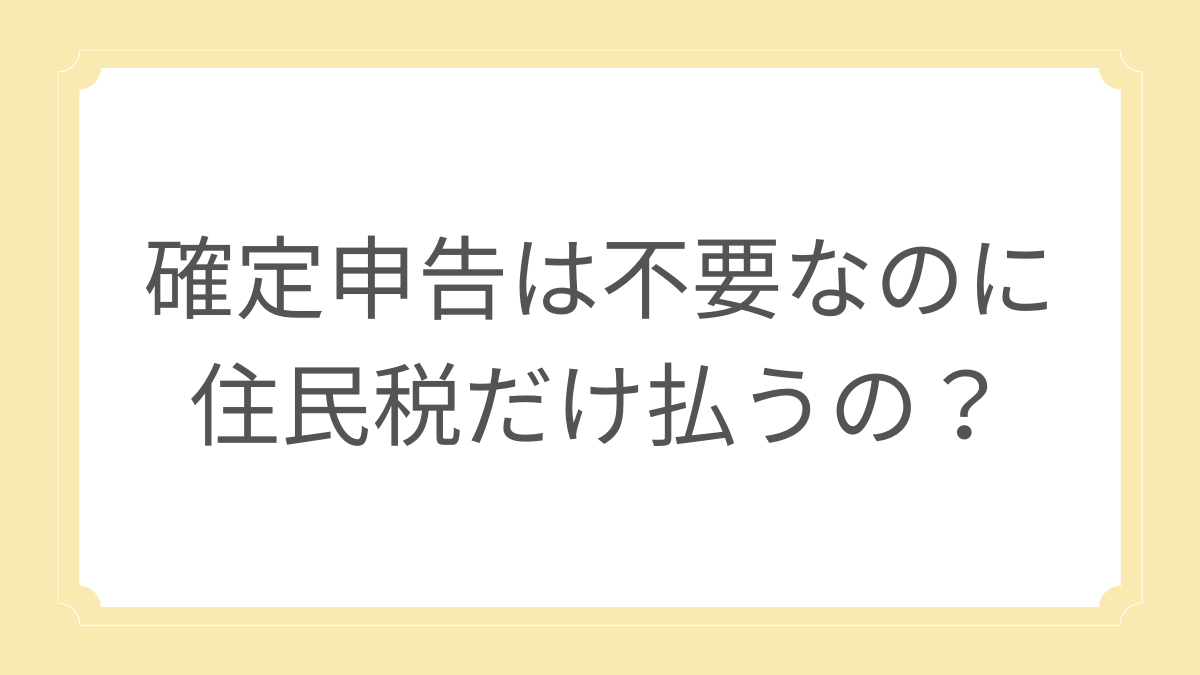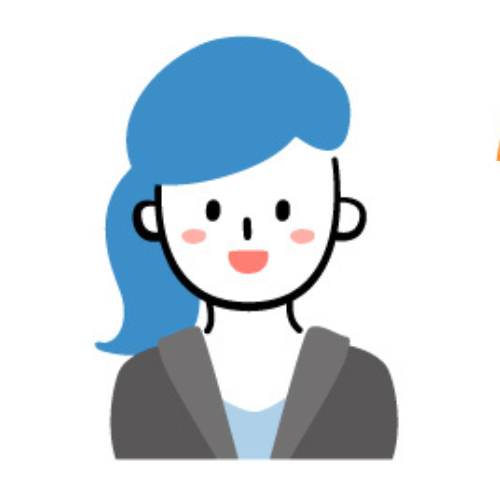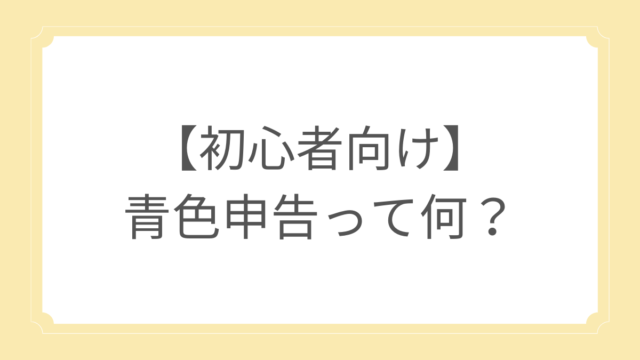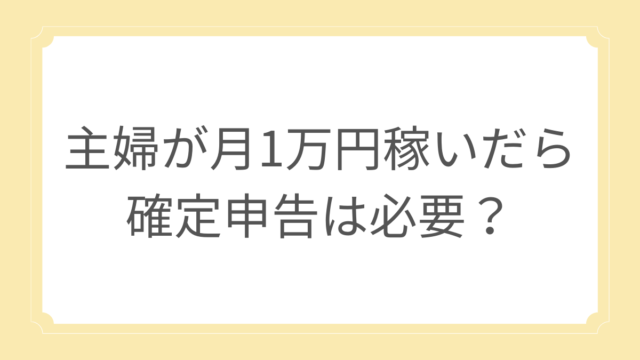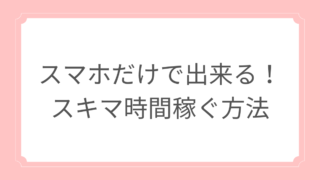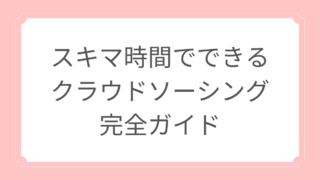副業初心者の主婦さんにとって、住民税は知っておきたい情報の一つです。
「確定申告と違うの?」「確定申告は不要なのに住民税だけ払うの?」と不安になったり、意味が分からずに混乱することも多いですよね。
収入が変動したり、副業を始めたりした場合にも、税金の支払いを見落とすことがあります。
この記事では、副業を始めたい主婦さんが困らないように分かりやすく住民税について解説します。
余計な心配をなくして副業に専念しましょう!
\無料で使える確定申告のお助けサービスもあります/
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告
住民税の計算方法
住民税は、単身世帯や控除対象配偶者、扶養親族の場合、年収が約100万円を超えると発生するのが一般的です。
月平均では100万÷12ヶ月=83,333.333…円となります。
住民税の計算方法
住民税=所得割+均等割+利子割+配当割+株式譲渡所得割
所得税の計算方法
所得税=課税所得金額✕税率-税額控除額
会社員の場合、原則として勤務先が年間所得を取りまとめ、従業員が住む地方自治体に住民税を納税します。
確定申告と住民税の違い

確定申告と住民税申告は、税金の支払いや申告を行う手続きですが、どちらも異なる目的や対象があります。
そもそも確定申告は国税の所得税や法人税を申告する手続きであり、住民税申告は地方自治体が徴収する住民税を申告する手続きです。
住民税は役所や区役所など地方自治体の税務課や税務署が窓口となります。
私も最初は混ざって考えていました。
専業主婦と兼業主婦の住民税申告の違い
専業主婦の場合:
専業主婦の場合、主たる収入源がないため、住民税申告においては配偶者の収入や所得が重要な要素となります。
配偶者の所得に応じて、住民税の計算や申告が行われます。
また、専業主婦の場合、副業収入やその他の所得がない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。例えば、住民税非課税世帯の特例や地方自治体の条例に基づく場合などが該当します。
兼業主婦の場合:
兼業主婦の場合、主な収入源として副業やパートタイムの仕事があります。
そのため、住民税申告においては、配偶者の収入だけでなく、自身の収入や所得も考慮する必要があります。
副業やパートタイムの収入がある場合は、その収入の金額や源泉徴収などについても申告する必要があります。
兼業主婦の場合は、配偶者の収入だけでなく、自身の収入に基づいて住民税が計算されることがあります。
以上が、専業主婦と兼業主婦の住民税申告における違いです。
専業主婦の場合は配偶者の収入が中心となりますが、兼業主婦の場合は自身の収入も考慮されます。
どちらの場合も、正確な情報をもとに適切な手続きを行うことが重要です。
均等割と所得割
個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得とは、企業などから受け取る収入から必要経費を差し引いた額をいいます。
所得割の税率は、所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。
※政令指定都市については、道府県民税が2%、市民税が8%になります。
所得=総収入−経費−控除
均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、その税額は5,000円(道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円)とされています。
※東日本大震災を踏まえ、都道府県や市町村が実施する防災費用を確保するため、2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられています。
各都道府県の【住民税 相談窓口】で問い合わせするのも良いと思います。
実際の課税では、これらの基準を踏まえ都道府県や市町村が自らの判断で税率を定め、納めるべき額を決定しています。
なお、道府県民税には、所得割・均等割のほかにも、一定の株式などによる利益についても課税の対象とするもの(利子割、配当割、株式等譲渡所得割)があります。
確定申告は不要なのに住民税だけ払うこともある
年間の所得が一定額以下である場合は、確定申告が不要となることがあります。
住民税は所得税や住民税の税率や控除額などが適用され、支払う税金が算出されます。
ただし、具体的な金額は地域やその他の条件によって異なるため、役所に詳細を確認することが重要です。
住民税の申告が必要な例外的なケース
住民税の申告が必要な例外的なケースには、以下のようなものがあります。
- 複数の源泉所得がある場合:複数の収入源がある場合、収入が一定額を超えると住民税の申告が必要になります。
- 配偶者控除を受ける場合:配偶者が所得を得ている場合でも、その配偶者からの特別給付がある場合など、一定の条件を満たす場合には住民税の申告が必要です。
- 特定の所得を得た場合:不動産所得や株式の売買による譲渡所得など、特定の所得を得た場合には住民税の申告が必要となります。
これらの場合、所得が一定額を超えるか、特定の条件を満たすかどうかに応じて、住民税の申告が必要となります。
住民税申告に必要な書類
住民税を申告する際に必要な書類には、所得証明書類や各種控除の証明書、本人確認書類などがあります。
これらの書類を準備しておくことが申告手続きのスムーズな進行に役立ちます。
住民税の計算方法
住民税の計算方法は、所得控除や税額控除、均等割などを考慮して行われます。具体的な計算手順は複雑ですが、役所や税務署で提供されるシミュレーションツールを利用することで、簡単に計算することができます。
住民税の納付方法
住民税の納付方法には、普通徴収や特別徴収などがあります。役所や区役所での窓口納付や銀行振込、郵便振替などが一般的です。
納付方法は地域や自治体によって異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。
申告しないとどうなる?
住民税の申告を怠った場合、滞納や未申告によるペナルティが発生する可能性があります。ペナルティの詳細については、役所や税務署の案内を参照しましょう。
確定申告との関係
住民税申告と確定申告は、どちらも税金の申告手続きですが、異なる目的や対象を持っています。
- 目的の違い:
- 住民税申告:地方自治体が徴収する住民税を申告する手続きです。主に住民税を対象とし、市町村や区などの地方自治体に納付されます。
- 確定申告:国税や法人税などを対象とした、国税庁に納付される所得税や法人税などを申告する手続きです。
- 対象の違い:
- 住民税申告:住民税や軽自動車税など地方自治体が徴収する税金を対象とします。
- 確定申告:国税庁が徴収する所得税や法人税、消費税などを対象とします。
- 手続きの時期:
- 住民税申告:一般的には年度末に行われます。
- 確定申告:所得税の場合は、通常3月15日までに申告書を提出する必要があります。
- 申告の義務:
- 住民税申告:一定の所得がある場合や、特定の条件を満たす場合に申告の義務が生じます。
- 確定申告:源泉徴収のない所得や、一定の所得水準を超えた場合に申告の義務が生じます。
- 関係性:
- 住民税申告と確定申告は、両方とも税金の申告手続きであり、個人の所得や資産に基づいて行われます。
- 一般的に、確定申告の際には住民税の申告書も提出することがありますが、住民税申告だけで確定申告を行うことはありません。
住民税申告と確定申告は、それぞれ異なる税金に関する手続きであり、役割や対象が異なるため、注意が必要です。
※確定申告を行った場合には、その申告書に住民税の情報を含めることがあります。確定申告を行った後、住民税申告書の提出を求められることがありますので、担当の税務署や役所に確認することが重要です。
まとめ
本記事では、住民税と確定申告の違いや申告手続きのポイントについて解説しました。
副業をしている主婦の方々も、この手続きをしっかり把握することで、円滑に税務を遂行することができます。
\無料で使える確定申告のお助けサービスもあります/
無料の確定申告自動化ソフト マネーフォワード クラウド確定申告
【初心者向け】主婦が月1万円稼いだら確定申告は必要?シュミレーションあり